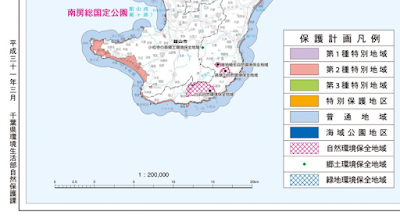2024年10月の出来事
写真:今年も咲いたハマナタマメの花.
なんだか意味ありげな機能美的な美しさが好きです.
マメ科の花としては逆さまという点で面白いのですが,その機能的な意味は?以前吸蜜しているハチを観ましたが,逆さまになって花に入り込んでいて大変そうで,その身体は花粉だらけでした.
先月アップしたクマバチに蜜をタダで持っていかれているハマゴウとは違って賢い進化をしたのでしょう.
こんな大きな豆が植えることもなく海岸に沢山あったら良い食料になっていそうなものですが,食べられないそうです.
なぜ食べられないのかは分かりませんが.
単に美味しくないというだけではないのでしょう.
縄文人は何かうまいこと料理して食べたりしなかったのかなあ~とか考えてしまいます.
少なくとも味見はしたことがあるでしょうね.
以下は今月のX(旧Twitter)投稿より引用し追記します.
投稿日が投稿内容の観察日ではない場合もあります.
写真はいつも通りこの月に撮影したものを文面の流れとあまり関係なく貼ってあり,それぞれ説明を入れてあります.
1日
8月の写真整理中です.
根本海岸で7/3発見のシロチドリ巣の囲いの様子ですが,人の侵入が防げていることが足跡で分かります.
普通に考えると生物保護中と看板に書いていて避けてもらえるのは,あたりまえのことと思うと思いますが,あたりまえに入ってくる人もいるので...
この時,既に卵は孵化していて雛が周辺を親子で歩き回って暮らしてる段階でした. 当初,卵が孵化したら囲いを撤去する予定でしたが,雛と親鳥は巣の周辺を安全地帯と感じている様子だったため,人と重機の侵入を防ぐ逃げ場としてキャンプ場運営期間中は囲いを残しました.
写真は前日8/14,中央に雛.
1日
8/21の平砂浦漂着カメの写真が出てきたので,ご参考に貼っておきます.
自転車はスケール代わりです.
海岸で遠目にこんな形状のものがあったらウミガメかもしれないのでご確認後に発見報告お願いいたします.
この場合は仰向けになっている,かなり大きな個体です.
写真:上空を警戒するシロチドリ幼鳥.
幼い頃に兄弟が上空から飛来した鳥に捕食された経験があったりする個体も多いのでしょう.
2日
8/19平砂浦で見かけた仲良しキアシシギ(左)とオバシギ(右).
オバシギはあまり見ないので.
幼羽ですね?
素敵な色柄.
4日
この夏,結構長い間この港の周辺に留まっていたウミネコ.
ケガをしている様子もなく,周辺で餌を探しながらこの位置でよく寛いでいて,ここの漁師さんも不思議がっていて,まるで漁船の見張りを自分の役割だと思ってるかのようでした.
8/23の写真です.
5日
産まれて4日のシロチドリの雛ですが,自分より随分大きなキアシシギやメダイチドリに混ざって採餌したり,餌探しに夢中になっていたら大波が寄せてビックリしたり既に様々な経験を積んでいました.
親鳥はそういう姿を適度な距離から見守っていて,すぐに訪れる親離れを意識しているかのようでした.
8/3根本海岸の写真です.
巣を作ってその中で親の運んでくる餌を食べながら育つ一般的な雛のイメージとはかけ離れた幼少期を過ごす鳥です.
こんな子たちが過ごしているのが夏の南房総の海岸なので,どうぞ気を付けてあげてください.
手前に写っているトラロープは巣(地面に産んだ卵)を保護するための囲いですが,孵化後も雛の避難場所として保護していたものです.
自分が産まれた巣のあった場所は親鳥も熟知している場所ですし,雛にとっても安心な場所のようです.
7日のぶら下げ
「今日はメダイチドリさん来ないのかな~」
と思ってそうな?孵化して11日のシロチドリ雛(写真右上).
この子の巣は写真右下のもう少し右側辺りの植生の合間にありました.
写真:海に流れ込む小川で水浴び中のシロチドリの幼鳥とその様子を見に来たメダイチドリ2羽.
このあとメダイチドリたちに追いやられます.
単独では不安だし,しかし身体の大きなメダイチドリたちの群れには仲間に入れてもらえないしという可哀そうな状態で越冬に入ろうとしています.
シロチドリの群れが来てくれればきっと仲間に入れてもらえるのでしょう.
写真:意地悪をされても仲良くしたい様子のシロチドリ幼鳥(左)と草に隠れているメダイチドリたち.
メダイチドリの様子には群れる習性が強い者に特有の習性を感じます.
写真:メダイチドリの群れと微妙な距離感で過ごしているシロチドリ幼鳥は群れが危険を感じて(この時は海岸に沿って人が歩いてきた)一斉に飛び立つ時に慌ててついて行く時があります.
しかし体も小さく,生まれて数カ月で飛翔経験も少ないシロチドリ幼鳥は到底ついて行けません.
写真の中ではクレジットの左上に白く小さなその姿が見えます.
それでも危険な中に単独で残るよりは良いと感じるのだと思いますがハヤブサの餌食になってしまわないか心配です.
しかし,うまく育てばシロチドリの中にあってはメダイチドリについて行く事で鍛え上げた筋力が優位に働いたりするかな?と思ったり.
8日
毎日のように朝から暑かったこの夏,このシロチドリの雛は巣を保護する為に設置した看板を低い位置から照り付ける日差しを避けるために上手に使っていました.
写真はしばらくそこでボーっとしてたところ.
それにしても今日はやっと涼しくなりましたね.
8/13の写真です.
生物を保護してるので立ち入り禁止と書いてあるのに突破するシロチドリ雛??
「わたしがその保護されてる生物なのですよ」とのこと.
この親子の様子も,同海岸で同時繁殖中だった別の親子同様,巣のあった場所を避難(休息)エリアとしていました.やはり孵化後も巣の周囲の一定の区域保護は人の出入りの多い海岸では雛の養育期に有効と考えます.
9日
8月台風で寄せたゴミ.
シロチドリの母親が何か言いたげです.
「人間が捨てたゴミは片付けてね」
「このゴミの奥にわたしの雛が隠れてるから近づかないで」
この場面での優先順位は雛ですのでゴミ拾いは次の機会に.
海岸の生きものの状況をよく観察してからビーチクリーンできるとベターですよね.
11日
先日のカヤックツアー.
やっと秋らしくなって涼しくなって幸せに漕げる本当のシーカヤック日和が増えてきました.
シーカヤックがそもそも北極圏先住民の乗り物だったことを考えると,そしてその構造を見て乗って体感してみると,なるほどこれは涼しい気候で使う舟なんだなあと知って頂けます.
ツアーでは写真を撮って参加者の方に送付共有させていただいております.また参加者の方に許可いただけた写真のみネット掲載しております.
写真:シーカヤックには最高の季節です.
写真は穏やかな日の館山湾.
11日
庭の枯葉を片付けずにそのままにして生物多様性を保つという記事。
庭→海岸
枯葉→海藻など漂着有機物
無脊椎動物→海岸性無脊椎動物
芝刈り機→重機
節約される時間→節約される税金
と置き換えるとほぼ海岸に置き換えられる内容でした。 地中に巣を作る蜂,植物の扱いについてはそのまま海岸も同じですし.
庭という最も掃除される頻度が高い場所についてこういう考えが出て来ていると分かって,海岸の掃除についての生物への配慮はこれから先の時代には思ったよりも当たり前な話として広げていける可能性を感じました.
14日
カヤック日記更新致しました.
Bloggerにも掲載してあります.
写真:台風の高波が寄せる潮間帯で採餌中のシロチドリの雛(写真中央),時折一発大波が来るので心配していましたが,雛はとても素早く波から逃げます.
手前に写っている沢山の棒とロープはこの雛が卵だった時に巣があった場所の周囲を保護するためのものでしたが,雛の避難場所を含めた活動範囲の中央であったため雛が育つ間,囲いを残しておきました.
15日
10月の真ん中となりましたが,暑いですね...
海辺の水浴び場も大人気でした.
種はハクセキレイとメダイチドリ.
野の者は自然の変化に合わせて生きることに慣れてますね.
人間も出来るだけ野に出て自然の変化を感じ取るようにすることが適応する為に大事な感じがしました.
写真:幻日に向かって飛んで行くトビ.
15日
この時期にこのサイズのグンバイヒルガオが根本海岸で見つかりました.
しかも水辺まで100mほどの海岸奥.
22日
9/1に投稿してあった白い花のハマゴウですが,見つけたのは2009年7月29日でした.
古いノートを別件で開いていて記録が出てきたのでメモがてら.
2018年には重機で群落周辺が平されてしまい消滅の危機がありましたが、なんとか復活しました.
22日
20年くらい前の写真のCDROMを見ていたのですが,中でも特に様子の変わっていた館山湾の某浜.
フィルムの2003年5月21日写真と海側からのは同9月.
ここの今の状況を知っている人は漁船の密度に驚くと思います.
あの頃まだ珍種だったシーカヤッカーに助言を下さり仲良くして下さった漁師さん達に感謝.
26日
2017年21号台風で崩れた砂丘の写真が出てきました.
今見てもゾッとします.
元々は緩やかな砂丘で撮影位置辺りまでに緩やかに傾斜していました.
この大型台風が神奈川に上陸したのは10月でしたし「今年はもう台風は来ないな」とか思ってたらフェイント掛けられそうなので気を引き締めなおしました.
27日
根本海岸のグンバイヒルガオをちらと見てきましたが,まだ元気でした.
写真:越冬にやって来たシロチドリの群れ.
海岸のこのような目立たない場所で静かに休んでいることが多いので特にビーチコーマーの方は漂着物のラインより上に入らずに同じ場所に長い時間帯罪などもできるだけ避けてご注意お願いいたします.
希少種となっている浜の鳥の貴重な休息場所がそこここに存在しています.
この写真の中には少なくとも15羽(シロチドリ13,ミユビシギ2)が休んでいますが実際にもかなり見つけることが難しいものです.
10月のXからの引用は以上です.
カヤック日記で引用する為に改めてその月のXの投稿を見てみると,投稿が少ない日,多い日,少ない月などあって自分では意識していなかった自分の状況が見返せて面白いなと思ったりしました.
10月の投稿はとても少なかったのですが,ちょうど論文を書いていてパソコンに向かえば,それに関する作業ばかりとなっていっためでした.
それで昔の写真資料を引っ張り出す機会が多かったため,昔の写真を投稿していたりもしています.
今回は植物の件をまとめていたのですが,過去20年余りの記録が必要だった為2000年代初頭辺りまで写真を遡って確認したりしていました.
それにしても外付けハードディスクは寿命があるはずですが,意外としっかり働いてくれて助かります.
最初に買った型のものは電源コードがその後使い続けているものとタイプが違い,しかも長い間使っていなかったためにどこかに行ってしまい(たしか断線して捨ててしまった記憶),写真が取り出せずにコードだけ購入してやっとデータが開けたりという状況もありました.
しかし昔の写真というのはやはり大切だなあと改めて感じました.
覚えている事なんてほんの少しですし,論文にするなどの場合には証拠ともなる記録ですので失くせません.
クラウドに上げておくという方法はまだ信用できずにいて,過去の記録はほとんど機器の中にしまってあるため大地震に大津波でも来れば過去四半世紀の記録が無くなってしまいます.
その時は自分自身が無くなってしまうかもしれないのですし,それでもいいかと感じなくもありませんが,記録は自分の為だけのものではないという事が最近強く感じられていて,論文なんて大変なものを書くのに時間と体力を費やす必要を感じたのもそのためです.
先月の日記でも少し書いたのでこれくらいにしますが,上手くいけば今回の某植物に関する南房総での記録を皆さんに知って頂けるようになりますので,その時は告知致します.
それにしても査読をする人は大変だと改めて感じました.
特に私のようなほぼほぼ素人の原稿では.感謝いたします.
写真:10/15発芽して間もないグンバイヒルガオを根本海岸の後浜内で発見しました.(写真は10/31の状態)
海岸から100メートルほど内陸側のキャンプシーズン中であればキャンパーが沢山いてクルマも行き来する位置でした.
こんな位置に種子が残されるような高潮は今までありませんから,漂着後に風で運ばれたか,キャンプ場の状況を考えると重機による整備の際に砂と共に運ばれたか,自動車のタイヤに挟まってなどなど,人の行動が関係していそうな事例でした.
高潮を浴びることもなく育つのに好適な環境かと思いましたが,実際には数日吹き荒れた風で砂が大量に移動したために消失してしまいました.
漂着種子が大きな群落を形成する事の難しさを改めて観ました.
写真:グンバイヒルガオの花も無事咲きました.
上の写真の例からも海岸性の植物がどこかの海岸からタネが流されて来て辿り着き芽を出して,花を咲かせるまで育つという事がそんなに簡単なことではない事は想像できると思います.
せっかく生きる場所を見つけた彼らが無事に生き続けられる環境が南房総にはまだ残っているという事の素晴らしさを南房総に関わる人々がもっと認識する必要を感じます.
写真:海浜植物は潮風や砂の堆積などには比較的強いのですが,踏みしめには強いとは言えないようです.
そもそも砂浜海岸にそのような大きな生き物が頻繁にやって来るという環境はあまり無いことからの不適応だと思います.
その中でヒトは砂浜海岸に暮らす生き物にとって,極地的に季節限定的に非常な高密度で現れる珍しい種として非常に危険な種となっているようです.(そのうえ乗り物までやって来ます)
ですので,海浜植物の観察には踏みしめについてとても気を使っています.
写真はグンバイヒルガオの花を記録しようとして,しかし本種を踏まないようにと無理な姿勢で撮影中な私の脚とグンバイヒルガオ.
お知らせ
6DORSALSのSNSリンク
随時活動報告,南房総の海の風景をお伝えしております.
是非フォローお願いいたします!